9月27日(土)10時〜12時 「父親のモンゴル抑留から考える」というテーマで瀬下 三留さん、「朝鮮からの脱出」というテーマで瀬下さんの中学時代の恩師であった隈元 亮一さんにお話ししていただきました。(場所:かごしま市民福祉プラザ5階)報告・記録者:松山 ゆかい
「父親のモンゴル抑留から考える」 瀬下 三留さん
2022年、シベリア抑留の実話をもとにした映画「ラーゲリより愛を込めて」が公開され、大ヒットを記録しました。
当時、終戦を迎えたにも関わらず、飢えや凍傷に苦しみながら抑留された多数の日本人がいました。シベリア抑留に比べ、モンゴルでも抑留があったことはあまり多く知られていません。
「抑留」という言葉が使われているのは、当時敗戦国であった日本は他国を貶めるような言葉を使うことができなかったからで、抑留の実態は「拉致」「強制労働」だと瀬下さんは考えます。
瀬下さんのお父様は満州の公主嶺で捕虜になり、アムール川を渡り、モンゴルの首都・ウランバートルの収容所で、木材伐採やレンガ小屋を作るために労働をしました。
真面目な日本人らしく、強制労働にも関わらず丁寧な仕事をしていたようで、現在でもモンゴルには抑留されていた日本人が造った建造物が多数残っています。
モンゴル抑留では、収容者14,000人のうち死者は1,700人で、1割以上が亡くなったそうです。
収容所では、極寒の屋外に並んで何度も繰り返し番号を言わされ、看守の機嫌が悪いとマンドリン銃を突きつけられることもあったそうです。
お父様の置かれていた状況を調べ、瀬下さんは以下のように考えます。
悲惨な戦争を起こしてはいけない。しかし、戦争はきっとまた起こる。起こってしまっても父のような経験を二度とさせてはいけない、繰り返してはいけない。しかし、決して敗けてはいけない。戦争をするなら勝たなければならない。
もちろん前提としては、戦争をしないために最大限の努力をする必要がある。ただ、国や国防の問題は地方自治体だけではどうすることもできない。「この国に戦争を仕掛けるととんでもないことが起こる」と他国に思わせることが大切。国は、国民が支持しなければ動かない。よって、国民が危機感を持つ必要がある。
「朝鮮からの脱出」 隈元 亮一さん
長年英語教師として務める中、知覧の中学校に赴任したことをきっかけに、小学生向けの平和学習へ携わることになります。「英霊崇拝」など当時支持された考えを押し付けることなく、小学生にも理解できる言葉で伝えることに奮闘されたそうです。
隈元さんは1942年に北朝鮮で生まれました。お父様は道庁職員でした。北朝鮮の家のことは、官舎の裏のりんご畑や積み木などをぼんやりと覚えているそうです。
終戦を迎えた1945年8月15日、知事以下の職員を集めて日本へ引き揚げるよう指令があり、隈元さんのお母様は、当時5歳のお姉様、3歳の亮一さん、生後5ヶ月の弟さんを連れて日本へ帰ることになります。
韓国や台湾に比べ、北朝鮮や中国からの引き揚げは、長い月日を要する困難なものでした。隈元さんの御一家は、8月15日に出発し、11日後の8月26日に韓国・釜山に到着します。
荷物は船に乗る前に全て捨てるよう命じられ、日本行きの船に乗りました。船の底はぎゅうぎゅう詰めで、立ちっぱなしだったそうです。
弟さんは船内で亡くなりました。船内で死亡した人は水葬されており、周りに「捨てろ」と言われましたが、お母様はそのまま連れて行き、博多港へ到着しました。そこから更に5日かけて、列車で鹿児島へ向かいます。遺体の発する腐敗臭もあり、列車の人にも「捨てろ」と言われますが、お母様は亡くなっていることを隠してあやすように弟さんを揺さぶり、故郷に連れて帰ります。
隈元さんは、焼け野原となり桜島がよく見える鹿児島の風景と、まだ赤ちゃんだった弟さんの足につかまりながら帰ったことをうっすらと覚えているそうです。
隈元さん御一家が鹿児島に帰ってから、いつまで経ってもお父様が帰ってくる気配がありません。「いつか帰ってくるのかな。」「向こうで家庭を持っているのかな。」と考えました。
中学生頃になると、父の2歳下の叔母様に、お父様はどんな人だったのか知りたくて、何度も尋ねに行きました。だんだん父がいないという実感が湧いてきましたが、お父様のつけた「亮一」という名前の由来を教えてもらったり、学生時代のお父様のエピソードを聞く中で、お父様との思い出はありませんが、お人柄を頭に浮かべることができたそうです。
50年後、お母様が83歳で亡くなります。遺品を整理する中で、お父様の同僚(長崎の方)から、お父様の死について記された手紙が出てきました。避難民救済にあたり、途中朝鮮人保安隊からの取り調べやソ連兵士からの掠奪など幾度となく大変な思いをしながら勤務を遂行したのち、チフスで亡くなっていました。
配偶者の死後に行政からお金をもらうためには死亡証明が必要なため、お母様の生活を案じた同僚の方から送られてきた手紙です。しかし、隈元さん御一家は、当時親戚も一緒に大所帯で暮らしていましたが、誰1人として手紙の存在をお母様から知らされていませんでした。
隈元さんは長崎へ手がかりを探しに行きますが、「原爆で焼けたため資料はない。」と言われ、手がかりは探せませんでした。なぜお母様が父の死を家族に隠したのか、考えました。
一つ目は、子どもたちに片親であると思わせたくなかったから。二つ目は、当時30歳だったお母様は、戦争未亡人であることを隠すことで自分の身を守りたかったから。隈元さんは、父が亡くなったのは戦争のせいだと強く感じています。
隈元さんが、授業の中で生徒へのお手本として書いた、生い立ちについて綴った文章を紹介します。
「父を返せ」 隈元 亮一
1942年、私は朝鮮で生まれました。
当時は、朝鮮は日本に属していました。
1945年、原子爆弾が広島と長崎に投下され、第二次世界大戦は終わりました。
私はまだ3歳でした。
母と姉、そして幼い弟と一緒に日本へ移る事になりました。
父は朝鮮に残りましたが、日本には戻ってきませんでした。数年後、父がチフスで亡くなったと聞きました。
朝鮮から日本に帰る途中、幼い弟は飢えで亡くなりました。母は亡くなった赤ん坊を背負い、博多まで列車に乗りました。その夏はとても暑く、木々や草は焼け福岡と鹿児島を結ぶ鉄道も一部壊れていました。
鹿児島に着くまで数日かかりました。
やがて弟の身体は臭い始め、周りの人々が赤ん坊を見つめました。「その子を列車から捨てろ」と誰かが言い出しました。
しかし、母は何も言わず弟を抱きしめ、まだ生きているかのように揺らしていました。
鹿児島に着くと、母は野原で弟を火葬し、骨を拾って戻ってきました。
母を待つ間、私と姉は小屋で最後の昼食を食べようとしましたが、それは兵隊に奪われました。私たちはすべてを失いました。弟の骨を除いて。
そして、ついに祖父母の家にたどり着いたのです。
隈元さんが紹介してくださった、広島の原爆詩集より抜粋した詩も掲載させていただきます。
「にんげんをかえせ」 峠 三吉
ちちをかえせ
ははをかえせ
としよりをかえせ
こどもをかえせ
私をかえせ
私につながるにんげんをかえせ
にんげんの にんげんのよのあるかぎり
くずれぬへいわを へいわをかえせ
お話を聞いた後、参加者の中に2名満州からの引き揚げ経験者がいたため、お話しをしていただきました。
Uさん(女性 昭和18年生れ)
2歳の頃に満州から引き揚げ、小学生の頃に両親が苦労した話を聞きました。引き揚げの船では、おにぎりを1個もらうために何時間も並びました。指宿に帰り着いた時には痩せ衰えていました。畳屋の商売をしており、満州でも経営は上手くいっていましたが、戦争により財産を失いました。戦争は言い換えれば喧嘩です。今も世界では続いています。偉い人がたくさんいるのに、なぜ話し合いだけで行動ができないのか、いつまでも戦争が終わらないのかと疑問に感じています。
Aさん (昭和17年生れ) (祖母と母親の引き揚げ時のメモ書きを基に本を出版されています。)
満州から引き揚げました。55歳の時に、祖母の日記を読んで自分の置かれていた状況を知り、残留孤児になっていた可能性もあったかもしれないと考えました。
その後、全員で感想や意見を発表しました。
・戦争をしないということが当たり前だと思う、そういう世の中になってほしい。
・自分なりの平和への取り組みとして、ホテルで勤務する中で、海外の方に笑顔で接し、英語であたたかい言葉をかけるようにしている。日本での記憶や印象として残ってほしい。
など、たくさんの平和に繋がる考えを聞くことができました。
今回お2人の話を聞き、どちらも戦後の出来事であるということが特に印象深く感じました。
終戦を迎えても、そこで一区切りではなく、苦しみは続いていたのだということを改めて実感します。
戦争を経験していない世代に1人でも多く、戦争がもたらした、戦後の悲惨な出来事の数々を知ってもらい、戦争と平和について考えるきっかけになってほしいです。
瀬下さんのお父様の収容所での出来事を聞き、戦争によってもたらされた理不尽さ、人としての尊厳を踏みにじられるような扱いに憤りを感じました。
私事ですが、隈元さんのお母様が自分の信念を通し、周りになんと言われようと弟さんの死を隠して故郷で弔い、父の死を家族に知らせず1人で抱え込んでいた頃の年齢と、私の年齢が変わらないことに強い衝撃を受けました。今の自分の生活と重ねると、生きた時代が違うとこんなにも状況が変わるのかと、胸がとても苦しくなります。
当時の人々の強さに触れ、私もその強さを少しでも持つことができるのなら、戦争で苦しんだ人々の体験や思いを確実に後世に伝え、平和を紡ぐために使っていきたいと改めて決心しました。



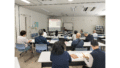
コメント