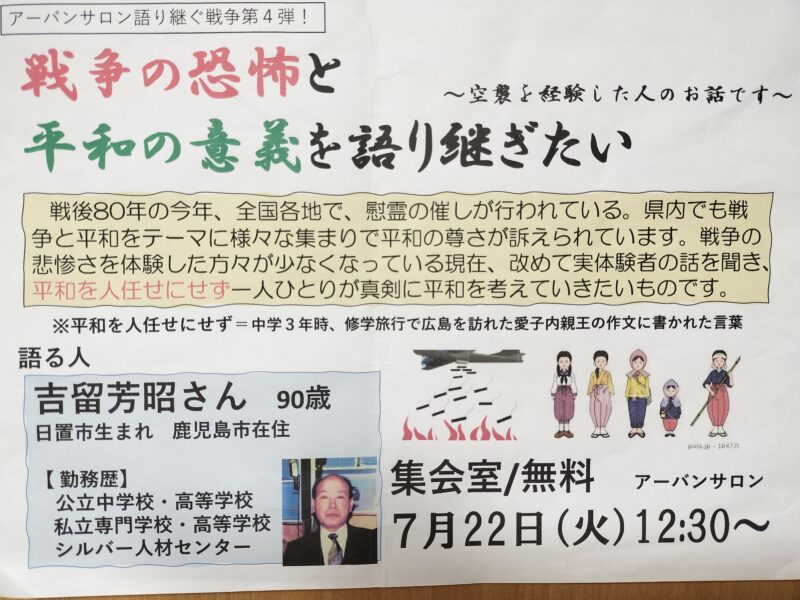
7月22日(火)「戦争を語り継ぐ集い」が、アーバンサロンで開かれました。
お話は、吉留芳昭さん(90歳)です。
以下、当日のお話を要約したものです。
吉留芳昭さんは、1935年(昭和10年)生まれで、戦前10年、戦後80年の人生を生きてこられました。
1945年8月15日の敗戦後、それまで教え込まれてきた社会の価値観が、戦後ガラリと変わり、新しい憲法のもとに一人の人間として、自分の思う生き方を選択できる自由を享受できている、しかし、今そのことが侵されようとしている未来があることを危惧しています。
2025年は日本にとって様々な意味で節目の年であると感じておられる。
近年の世界情勢、特にロシアのウクライナ侵攻や中東のイスラエル・ガザ紛争について、テレビ画面に映し出される悲惨は状況を目にしては、腹が立ち、テレビに向かって、つい、憤ってしまう。これらの紛争を止められない国連の無力さに失望感を感じている。 これらの出来事がきっかけとなり、吉留さんは戦争について語る活動を始めるようになりました。
まず、日本の近代戦争の歴史を振り返り、日清戦争(1894年)、日露戦争(1904年)、第一次世界大戦と、小さな国である日本が大国と戦ってきた歴史の説明、これらの戦争で日本は勝利したものの、その後の昭和期に入り、満州事変(1931年)から始まる大陸進出、日中戦争(1937年)、そして太平洋戦争(1941年)へと続いていく。
戦時中の日本社会について、国家総動員法による人と物の統制、国民学校での教育では、天皇崇拝が強調され、「今日も学校に行けるのは兵隊さんのおかげです」といった教育を受けたこと、隣組制度による末端組織の管理、女性の役割の変化など、子供頃に目にした光景を話されました。
母親を含めた女性たちが、男性達がいない中、消防団員の役目を担ったり、竹やり訓練をしたり、していた様子など。吉留さんは、10人兄弟の10番目でお母さんも高齢になっておられたようですが、それでも、若い女性たちに加わり、竹やり訓練に励んでいたまた、昭和15年(1940年)には多子家族の表彰制度があったそうです。
太平洋戦争の経過について、初期の南方進出から次第に日本軍は、劣勢になってき、特に特別攻撃隊(特攻隊)の若者たちは、天皇のために命を捧げ、その犠牲については、「玉砕」という言葉で美化されたことを教えてくださいました。
「忘れられないのが、1945年の1月1日、年の初めで学校は登校日で、元旦の式典がありました。その時に。青空に薩摩半島の南のほうから悠々とですね。小さい真っ白な飛行隊の悠々と飛んでいる。これが後で知ったことですけれども、偵察隊で撮影をしていたみたいなのです。
そして、3月18日、山の東の方から低空飛行の編隊規模でやってきました。相手の操縦兵が見えるわけです。その時、村の小学校が爆撃をされました。
平和を維持させることは、今日とても難しいように感じてきています。しかし、戦後80年平和が維持できてきたのは、世界にはない、平和憲法のおかげだと思っています。私はいつも憲法の冊子を持ち歩いています。
教員をしていたので、戦後教え子を再び戦場へ行かすな、ということでいろいろやってきました。そして、今、生きている限りは戦争中を生きた者として、二度と戦争を起こしてはいけないと願いつつ、戦争を語り継いでいきたいと思っています。」
感想 山下春美
吉留さんが、ご自分の体験から、「語り継ぐことが平和を維持することに繋がる」と、願いを込めて、活動されていることに、私はいつも元気をもらいます。
吉留さんと重なる時代を生きることができたことが、とても有難いです。

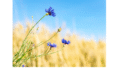
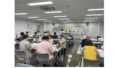
コメント