「かごしま福祉と憲法を考える会」の天羽浩一さんより、今週末に「戦争を語り継ぐことは、戦争抑止力になるのか?」というテーマで開催する「グループワーク」への議事提起を頂きましたので、掲載させていただきます。
1.昨今の会見・挨拶より
天皇誕生日会見(2月23日)
「(略)戦争を体験した世代から、戦争を知らない世代に悲惨な体験や歴史が伝えられていくことが大切であると考えております。(略)国内各地で若い人たちが戦争を知ろうとし、次の世代の語り部として育ち、戦中戦後の苦労を語り継ぐ活動が進められていることは、戦後80年を迎える今日、いっそう意義深いものとなっていると思います。(略)」
日米硫黄島戦没者合同慰霊追悼顕彰式(3月29日)での石破首相の挨拶から
「(略)戦争の惨禍を決して繰り返すことがないよう、われわれは、歴史に真摯に向かい合いながら、悲惨な戦争体験を、世代を超えて語り継いでいく努力を続けていかなければなりません(略)」
現天皇は祖父(昭和天皇)の負の遺産を現上皇(平成天皇)から引き継ぎ「過去の歴史に対する理解を深め、平和を愛する心を育んでいくことが大切」と平和・非戦の思いを述べている。また現上皇は天皇在位時、節目節目で立場上限界がある表現ではあるが戦争責任、加害責任について言及してきた。
石破首相は憲法9条2項の廃止と、国防軍の設置を主張する超タカ派政治家として知られてきた。(現在は少数与党の首相として立場上、自らの主張は封印し、4項目改憲にシフトしているが)
戦争を語り継ぐという行為は、イデオロギーや立場に関係なく、戦争を忌避し、平和を希求する人間としての普遍的な心情をあらわすものと言える。 現天皇も石破首相もまた平和を希求し、戦争を忌避する一人であるといえる。
2.語り継ぐ・継がれること
語り継ぐ、継がれる内容は、且って兵士だった者の証言、また妻であり、母であり、恋人であり、兄であり、弟であり、子であり、友であった者たちの証言、兵士であった者でも、どこに派兵されていたのか、また階級は、そしてどういう体験をしたのか、さらに被害を語る者、ごく稀だが戦争責任や加害を語る者、立場により人により語る内容は多様である。それぞれの体験、証言を貴重なものとしてそのまま受け取ること、しかしそれはあくまでそれぞれの方々の取替のきかない個別体験(特殊性)であることをわきまえておく必要がある。
戦争を語りつぐことが「戦争を忌避し、平和を希求する人間としての普遍的な心情である」点において、一人ひとりの人に非戦=抑止の心情をもたらすと言えるが、実際に戦争抑止力になるかどうかはまた別次元の問題があると思う。
3. 碑文
「安らかに眠って下さい 過ちは繰返しませぬから」という広島原爆慰霊碑に刻まれた碑文について、且つて幾たびか碑文論争があった。誰が過ちを犯したのか、誰が過ちを繰返さないと言っているのか、主語と文意が明確ではないからだ。
これについて広島市が公式見解で「すべての人びとが原爆犠牲者の冥福を祈り戦争という過ちを再び繰り返さないことを誓う言葉である。過去の悲しみに耐え憎しみを乗り越えて全人類の共存と繁栄を願い真の世界平和の実現を祈念するヒロシマの心がここに刻まれている」とし、過ちはすべての人類を指し、過ちを繰り返さないというのも全人類を指しているとしている。戦争犯罪や誰に原爆投下の責任があるかなどを問うているわけではない。
オバマ元米大統領のヒロシマ演説(2016年)は「空から死が降ってきて、世界は一変した。」と主体なき無責任な言葉から始まった。原爆投下の責任を問うことなく、「水に流して祈る」ことしかできない現実がある。
戦争を語り継ぐ、原爆被害を語り継ぐことで共通していることは、戦争や原爆被害の悲惨を語り継ぐことで、戦争被害を原爆被害を可視化させるが、何故戦争が起こったか、なぜ原爆が投下されたか、あるいはその責任は何処にあるのかを問わないということである。また被害は語るが加害が語られることは稀である。キーワードは「なぜ起こった」「責任の所在」「加害を語る」。しかし原因も責任も被害も加害も深い祈りということのなかに解消してしまう傾向があると感じる。
4.「NO WAR! NO GENOCIDE!」(戦争反対!大量虐殺反対!)
「NO WAR! NO GENOCIDE!」は誰に対して呼びかけているのか明確ではない。プーチンやネタニアフに対してか、ゼレンスキーやNATOに対してもか、あるいはロシアやイスラエルの国民に対してか、それとも日本政府にか、私たち日本国民に対してか、ヒロシマの碑文にならえば、全人類への呼びかけとなるのかもしれない。しかし全人類に呼び掛けるというのではあまりに具体性を欠き、おこがましくもあり、妄想ともいえよう。あるいは「私は戦争に反対している人だ」という免罪符にすぎないのかもしれない。
スタンディングは無意味だ、時間の無駄だと思う人もいるだろう。確かに空虚であり、無力である。しかし今のところ意思を明らかにする数少ない方法のなかの一つ(選択肢)である。小さな声をつなげ広げていくこと、それはささやかな自己満足といえるのかもしれない。
一方、確かな現実として、「核兵器禁止条約の署名と締結を求める具体的な運動」が国際的に結実しつつある。ごく少数の核保有国を中心に「核による抑止」の流れが強まっているが、大半の核非保有国を中心に核兵器廃絶を求める多数派小国連合が生まれつつある。
日本でも被団協のノーベル賞受賞を契機に、核廃絶の運動は多数とは言えないが、無力ではないというレベルまで到達していると言える。
5. 最後に
戦争を語り継ぐ、原爆慰霊碑、スタンディングと3つの語り・祈り・行動について紹介してきたが、実際にどのようにして平和が保障されるか、何が戦争抑止になるかという点についていえば、さらに一歩踏み込まなければならない課題があると思う。
それは「軍事抑止力による平和構築」(1案)と「平和外交による戦争回避」(2案)という二つの相異なる考え方への複眼的アプローチ法である。
前者と後者では平和構築の方法として極端な開きがある。一方の極「核武装と集団的自衛権による臨戦態勢の構築」、もう一方の極「一切の武力を放棄した丸腰全方位平和外交」まで。この両極の間はスペクトラムを形成している。互いに心を開く対話を通し、スペクトラムの中から合意できる色合いを見出していく方法を見つける必要だと思う。それは市民レベルの対話、政治レベルでの対話、国会の中での対話、あらゆるレベルで繰り返し対話を続け積み重ねていくことだと思う。
「民主主義は、個人の自律的な理性を信頼し、あらゆる政治的な見解がそれぞれ相対的な真理性と合理性を持つと前提する多元的な世界観に基づくものであり、対等な同僚市民たちの間の尊重と博愛に基づく自立的で協力的な公的な意思決定を本質とする」(尹大統領罷免に関する韓国大法院判決文から)
次回、平和論としての抑止論と外交論の交錯する地点を探す対話素材を提供します。
(追記)
国際法によって戦争は否定されているので、現在は戦争とは言わずに自衛権発動という。アメリカもロシアも、イスラエルも自衛権の発動に伴う軍事行動という位置づけで、「平和」のために軍事行動(実質は戦争と虐殺)が行われている。その自衛権発動を決めるのは内閣(大統領府)・軍部の中の数人程度である。
平和の旗の下に、戦争に反対するという名目で軍事行動が開始される。ごく数人の自衛権発動権限者(戦争遂行権限者)に徹底的な歯止めを加える力が国民にあるのかどうかが問われるのではないか。この間の韓国戒厳令発令に見られた韓国民の市民力は大統領を罷免に追い込んだ。翻って、日本でこのようなことが起こったら、どうだろうか。お上が決めたことと、心にわだかまりを抱えつつ首相の決定(自衛権発動=戦争開始)に従っていくのではないか。

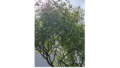

コメント
天羽さんの投稿を興味深く拝見しました。
長年、平和活動に従事されている思いを深く感じさせる文面でした。
私としては、同調する部分や相対する部分を持ちながら読ませていただきました。
「それは「軍事抑止力による平和構築」(1案)と「平和外交による戦争回避」(2案)という二つの相異なる考え方への複眼的アプローチ法である。
前者と後者では平和構築の方法として極端な開きがある。一方の極「核武装と集団的自衛権による臨戦態勢の構築」、もう一方の極「一切の武力を放棄した丸腰全方位平和外交」まで。この両極の間はスペクトラムを形成している。互いに心を開く対話を通し、スペクトラムの中から合意できる色合いを見出していく方法を見つける必要だと思う。それは市民レベルの対話、政治レベルでの対話、国会の中での対話、あらゆるレベルで繰り返し対話を続け積み重ねていくことだと思う。」
最後にの章に書かれている部分は特に命題だろうと思います。
コメント、ありがとうございます。戦争抑止力についてどのような方法論をとなえるか、意見が違っていたとしても、平和な社会であってほしい、と国民は願っています。なぜ、国民の思いと国、政府の意思は、異なるのでしょうか?国の方向性を決めているのは、一体何なのでしょうか?