4月26日(土)10時~12時 参加者20名 「戦争を語り継ぐことは、戦争抑止になるのか?」とうテーマで
グループディスカッションをしました。
後半、7人に発表していただいた内容を記録としてまとめました。(話された言葉に近い形で書いています。)
「戦争を語り継ぐことが、戦争抑止力になるのか?」リレートーク
Aさん:
80年間、日本は戦争をしていませんので、戦争しているウクライナとか、ガザとか、ああいうところの戦争とはちょっと別にして、日本がいろんなこういう情勢が変化してきて、外国と戦うようになることをやめないかんということだと私は解釈しています。そのためには、我々は戦争を知らない世代なのですけれども、いろんな行政が慰霊祭や展示会をほぼ毎年中行事としてやっています。
いろんなところで、それにまず参加して、いろんな現状を知るということ。
それから私ができることは、もうすぐ鹿児島大空襲の遭った6月17日が来ますけれども、鹿児島市役所前のみなと大通り公園で太平洋戦争民間犠牲者慰霊碑「人間之碑」への献花をする追悼行事に参加後、自分の町内会にある町内会の慰霊碑に花を捧げます。
そういうこと、何も他人に頼んだこともございません。私は自分がやりたいからやっているだけのことです。さっき慰霊碑の話が出ましたけど、そういうまず小さな慰霊碑に関心を持ってもらうということですね。またそれまで知らなかった新しい話を知ったならばそういう慰霊碑を立てることに力を注いでほしい。石で作ってしまえば300年400年は残りますので。
誰も語らず、人がいなくても、戦争は悲惨なんだということを訴えることもできる。我々、一般市民ができることは、こういうことだと思います。為政者が、どうのこうのと言っても、我々の国のレベルで利害を考える人たちはあまりにも違いすぎるんですよね。だから我々ができれば、そんなことじゃないかなと思います。
Yさん:
皆さんこんにちは。私もこの会に2 3回ほど参加させていただきまして、鹿児島ほたる会という会がありまして、その中で毎月一回、知覧に行き、平和を祈るという気持ちで活動をしています。
今日、グループディスカッションをする中でいろんな意見がありました。もちろん特攻のことについてもです。 私が知覧に初めて行ったのは、小学校の遠足の時がきっかけです。それからずっと行っておらず、県外から来た人が行きたいということでお連れしたのが、約二年ぐらい前です。
それから行くきっかけがどんどん増えていったんですけども、いろんな知識といろんな方々を案内するようになりました。鹿屋も含め、知覧も含め、そして去年、慰霊祭にも参加しました。
本当にまず自分たち、こういう活動されている方たちとか、こういう場に来る方たちは、もちろん語り継ぐということが大切なんですけれども、それ以上に知るきっかけを作る、知るっていうところ、いろんな個人の発言だったり、メディアであったりとかっていうような、知るっていうところからがまず始まりなのかな、っていうふうに感じました。
そういう意味合いでは今日のテーマにある、語り継ぐということの必要性ということは、必要だと思うのですけど、それの中にやっぱりこうグループディスカッションした中でもそれぞれの意見、お互いの意見を、いろんなところを取り入れながら、この人はこう考えているという、本当に意見一つ違えば、それこそ戦争になってしまうことでもあると思いますね。
そういう、この和をもって、いうところの日本人の良さとか、日本の素晴らしさっていうところも含めて、語り継いでいく中で、戦争はダメだよって言うよりは、私自身はこの平和な世の中が続くためには、自分たち、私たちは何ができるのかっていうところを考えて、今いろんな人にお伝えしているので、この平和になるために何ができるかっていうところを考えていくとなると、もっといろんな人からも知るきっかけになるのかなというふうに私は思いました。
Kさん:
お話を伺う中で、戦跡を見て、当時を語る人がいるという話がすごい印象に残って。その戦跡が持つ意味って、やっぱりこう語れる人が少なくなるから、どんな戦跡が語りかけるんだっていうものではなくて、やっぱりまだ語ろうという、語りたくないって思っている人がそれを見て、やっぱり忘れられない記憶があって、残し、伝え継いでほしいという思いがある。そのきっかけが戦跡であったり、慰霊碑であったりっていうものがあるんだなと、強く印象に残りました。鹿児島は残されているものがたくさんあって、すごいなぁ、と。私はまだ知らないものもたくさんあるので、そこを回って、そこに住んでいて生活していた人たちが、どういう体験をしたのかっていうのは、今後も学んでいきたいなというふうに思いました。
また一方で、こういった戦争体験を語ったり、その抑止力になるかっていうテーマを考えた時って、やっぱりこう解決策っていうものはなくて、日々どうやったらこの戦争の記憶を継承していけるんだろうって考え続けることがやっぱりもちろん大切だなと思いました。
またその戦争そのものの話がメインになってくるんですけれども、そうではなくて、やっぱその前後でどういう出来事があったのかっていうことを考えることも、その戦争が起きた意味とか、戦争が残していったもの、残らなかったもの、残さなかったもの、奪っていったものについても、これからも考え、意見を交換し合うことは、すごく重要な取り組みだなと思いました。今日はありがとうございました
Sさん:
グループ4人で、いろんなお話をさせていただきました。いろんな考えがあるわけです。現実に日本では80年間、今のところ、戦争で武器を使う、武力を使う戦争は避けてくれたわけですけれども、それ以外にもいろんな侵略があるんじゃないですか、ということは、私は言いました。
戦争を語る、語り継ぐっていうことは抑止力になるのかという、山下さんの意見があるわけですけども、私は全くならないとは思わないんです。ただ、その中で、どうやったら戦争を防げるのかということの具体性というものが、必要ではないかと思います。これを言うと非常には長くなるんで、とりあえず終わります。ありがとうございました。
Mさん:
私は昭和文化の研究をしています。
戦争を語り継ぐことを抑止力になるのか。喋らなかったら誰もわからない、知らない。だから始めるしかないというのが私の中にあります。昭和文化研究の中で、必ず戦争中の話をします。
ただ、語るだけではなく、当時、そういうことがあったなとか、楽しいこともあれば、悲しいこともある、ありのままを語ることかなと思ってお話をしています。
今日はその当時を知るという意味合いで、当時のものをわたくしは持ってお話をします。これはB29がばらまいた「戦争やめなさい」というビラであったり、祖父母のうちから出てきた配給権とか。色々あるんです。スパイにご注意しなさいっていう回覧板のチラシもあります。
私は、大学生に話をする機会があるのですが、生徒が関心を引くようにいろいろ工夫をします。例えば、この「スパイに注意しなさい。」というチラシを見せて、もし、スマホでもこの回覧板のチラシが出てきたらどう思うかなっていうふうに意見を聞いたりしています。
人を監視せよって書いてあるんです。普通に。それを見たら、今の感覚でもやっぱ、怖いなって。こんなのが回ってきたら。だから行き着くところは戦争が起こると何が起こるのかなと、いうところから、調べていったらいいのではないかと思います。
戦争の前後を知ることは大事なことです。要するに原因は何になるのか、戦争が起きた原因は何なのかで。
世界を見て、日本だけじゃない、世界でも今、同じようなことが起きています。ロシア、ウクライナでも。
結局、その始まった理由ってなんだろうって。結局領土で、ここが豊かだから、ぶんどってやろうっと。日本もかつて、満州、今の中国東北の人たちの土地を狙われたわけです。やっぱり理由はあります。抑止力は結局、世界を見て、そして原因を調べていったらよろしいんではないかというご意見にまとめさせていただきます。
Yさん:
今日は、グループワークで自分の知らなかったことを知ることが出来て良かったです。
戦争を語り継ぐっていうのは、多くが戦争の悲惨さとか被害について語られてきたし、もっともっと語られてない被害とか悲惨さというのがあるし、その前の戦争だけじゃなくて、今、起こっているウクライナでの戦争そのものの悲惨さだとか、大変さっていうものを語り継ぐっていうことなんだろうなっていうふうに思います。
ただ、一方によってこの悲惨さだとか被害を語るだけで本当に充分なのかなっていうのはですね、語られるべき内容としては、さっきKさんも言われたように、戦争の前後で何が起きたのかということを知る。
加藤陽子さんの著作に「それでも日本人は『戦争』を選んだ」というのがあります。国民は戦争を支持した国民が選んだんだっていう。やっぱり多くの国民が、実はその前に、戦争に賛成して、協力して、もっともっとやれっと、いうふうに、やってきたんだっていう事実を、やっぱり忘れてはならない。
実は今、ロシアでもプーチン大統領にいろんな不正があって、いろんなことがあったとしても、大変な支持を受けているんだということは事実なんです。イスラエルの国内でもです、ガザでの戦争でも、国民がやっぱり支持してるっていう人たちがたくさんいらっしゃるし、アメリカでも、この軍拡のそういった政権にトランプさんに熱狂して投票した人がいます。日本でもそういった、軍拡を40何兆円っていうふうにする、という政策を支持する政治家に多くの人が投票するんですね。やっぱり支持している人があって、そういったなぜ戦争の道をあの国民が選ぶのか、選んでしまったのかっていうことを、もっともっと、なぜそうだったのかっていうことを語り、悲惨さだけじゃなくて、語っていくっていうのが必要じゃないかな。
それはきっと、戦争の抑止力になるのではないかと思います。
戦争の起きた理由っていうのは、いろんな理由で起きると思うんです。経済的なこと、あるいはいろんな愛国心とか、民族主義的な、そういうことを、学問の自由だとか、そういったことをさっきのグループ討論でも、語られたんです。
そういったことはなんで戦争が起きて、国民がそれを支持していったのか、日本国もそうだし、世界にいろんな、今起きていることを、語ることとも、悲惨さ、被害を語るだけではなくて大事なことではないかと私は思いました。
Tさん:
今日は、いろんなグループのところを回って、お話を聞かせていただきました。
各グループ回って、感じたことは、一応テーマとしては、戦争を語り継ぐことは抑止力になるのかっていうテーマだったんですが、戦争を語り継ぐっていうのと、それが戦争抑止力になるかっていうのは、私が聞いたグループでの話内では、少し離れた話で、戦争を語り継いだことがイコールそのまま直接抑止力になるのかっていうふうなことであって、別に根拠もないですし、必ずそうなるとは限らないというふうに思うんですが。
戦争抑止力。戦争を起こさないためには、そもそも戦争の、悲惨さであったり、平和の大切さを知る人を増やすこと。それでは、知る人を増やすためには、無関心な人にどう知ってもらえるかという、知る機会を増やすことがやっぱり大切だなっていうふうに、常々感じています。
Kさんが言われていましたが、そもそも戦争が起こる理由っていうのをしっかり、とことん突き詰めて、それを知ってからこそ、抑止力につながる。
戦争を起こさないために、必要なことが何なのかということが見えてくると思うので、まずはその原因をとことん突き止めたら、戦争を起こさないっていうふうな方法の一つとして、戦争を語り継ぐこと、ということも、見えてくるかもしれないです。だからこそ、原因を追求することが、大事になってくるんじゃないかなというふうに改めて思ったところでした。ありがとうございます。
山下:感想
どうしてもこの質問を出すと、答えを握りしめて、帰りたくなってしまうんですけれども、ぜひ今日はモヤモヤした感じを持って帰って、ずっと一生その問いを持ち続けていけるような、私自身、歩みをしていけたらと思っています。本当に貴重な皆さんからの意見をいただいたことを、自分自身の活動として、そしてそれを皆さんと一緒につなげていきたいと思います。ありがとうございました。


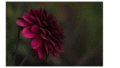
コメント