
本日は、川商ホール(前:鹿児島市民文化ホール)で、生協コープ主催の「平和の集い」が開催され、私(山下)は、オンライン参加しました。
今回は、いちき串木野市の石神斉也さん(91歳)が13歳の時、鹿児島市加治屋町での空襲体験を語ってくださいました。
石神さんについては、このブログでも紹介しておりますので、ご覧ください。
「昭和20年6月17日 鹿児島大空襲体験を聞きに行く」
石神斉也さんは、昭和20年、父親が山下小学校の教員をされていたので、鹿児島市加治屋町敬愛幼稚園の隣に住んでいました。
6月17日の深夜近く、突然起こされ、着の身着のままで出て行いったが、周りは真っ暗、中心部から人がどんどん逃げてくる。雨のように、焼夷弾が降ってくる。頭に落ちると、油で、髪が燃え、慌てて振り落とす・・。家の敷地内に掘っていた防空壕は、当時雨が降り続いていたため水がたまり、入れなかったので近くの甲突川の土手に逃げた。
「母親は、強いもんですよ。布団を家から持ってきて、それに水をかけて、子供たちにかぶせてくれました。父親は、というと、東郷平八郎の掛け軸と先祖代々の刀3本を抱きしめて、空をじっと見ていました。」
その夜は、隣家に泊めてもらい、次の日父の郷里のいちき串木野市に行くため、西駅(現:中央駅)に向かいました。
「不思議と私は、死体を見なかったのです。見たのは、次の日、隣りの家に親子3人で住んでいた家族の父親が中風で動けず、逃げ遅れたのか、白い布がかぶせてあったのを見ただけでした。」
「戦争では決して兵隊さんが、戦いだけで亡くなったのではありません。それ以上に、餓死、沈没死(船の移動中)、自決などで多くの人が亡くなりました。」
「また、死んだのは、人間だけではありませんでした。上野動物園のゾウが殺されました。ゾウを注射で殺そうとしたら、皮膚が厚く、通らず、食べ物に毒を混ぜて殺そうとしたら、毒入りがわかり、食べず、とうとう、食べ物を与えず、餓死させる手段を取ったそうです。餌をもらえないゾウは、どうしてだろう、と思い、そうだ、芸をしたら、餌をもらえるはずだ、と思い、前足を上げて、芸をしてみせた、と同時に力尽きて死んでしまったのです。」
当時、「欲しがりません 勝つまでは」という歌がありました。
♪どんなに短い 鉛筆も どんな小さい 紙片も 無駄にしないで使ひます
さうです 僕たち 私たち 欲しがりません 勝つまでは
♪靴や洋服 新しく つくることより 役に立つ 強い体をつくります
さうです 銃後も戦地です 欲しがりません 勝つまでは
「この銃後も戦地です、という歌詞から、本土も戦地、ということで、無差別の爆弾が落とされたのです。」
「その一方で、このような替歌を歌われていました。」
♪「僕は 軍人大キライ 今に小サクナッタナラ
オッカサンニ 抱カレテ チチノンデ 一銭 モラッテ アメ 買イニ」
♪「負ケテ来ルゾト 勇マシク 誓ッテ 国ヲ出タカラハ
手柄ナンゾハ知ルモノカ 退却ラッパ 聞ク度ニ ドンドン逃ゲ出ス勇マシサ」
戦争が終わり、鹿児島市内の高校に通い出した時、伊敷の練兵隊の所に仮の校舎がありました。その時、アメリカ兵に「ギブミー、チューインガム」と言ったり、アメリカ兵がトイレの便座に座って、小便をしているのを見て、「違っているんだぁ・・」と驚いたことを覚えています。
この『戦争を語り継ぐ』(本の表紙を見せながら)という本の前書きに、著者が、「若い人が『B29って、爆撃機?鉛筆の名前だと思った。エンピツは、2Bとか、HBとかあるでしょ。』という話に、『あー、戦争って遠い昔になったんだぁ~」と書かれていました。
私は、教員として、戦争を語り継ぎ、戦争では平和は語り継げない。だからこそ、憲法の大切さを伝えていきたい。
「みなさん、希望を持とうではありませんか。次の行動に移していこうではなりませんか。」
編集後記 山下春美
私が石神さん宅に伺い、お話を聞いたのは、今年2月28日でした。その時は、90歳でしたが、3月にお誕生日を迎えられ、91歳になっておられました。空襲、戦争体験をはっきり覚えておられ、語ってくださる最後の年代だと思います。私たちは、石神さんが語る戦争の恐ろしさを決して忘れずにいる、そのことが、自分の次の行動を創り出していくような気がします。
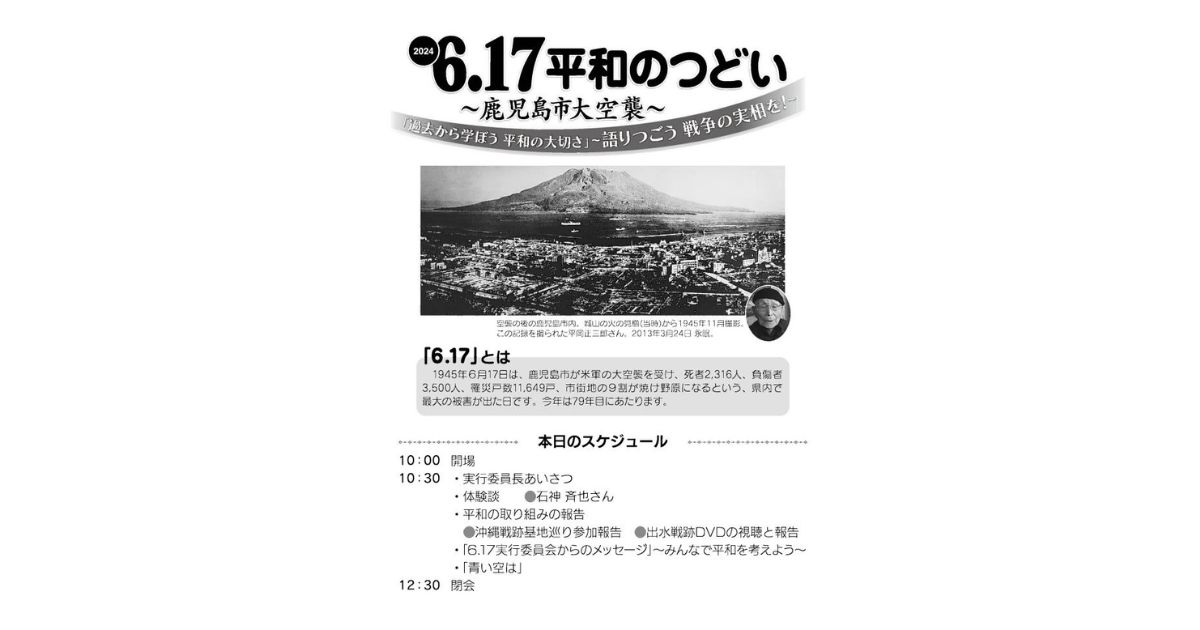

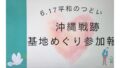
コメント
当時、”負ケテ来ルゾト勇シク”と替え歌されていた事など初めて知りました。
コメント、ありがとうございます。私も、この替歌は初めて知りまして、国民の本音がうまく表現されているのではないかと感動しました。この替歌は私たちの未来の行動指針の参考になるのではないかと思います。